2024/07/24
国府の餅屋で朴葉餅の作るところを見てきました
飛騨国府の餅屋さんが、どこから朴葉を採ってきて、どうやって朴葉餅を作っているのか。そして、なぜ朴葉餅を作り続けているのか聞いてきました。

今回は、高山市国府町の餅屋の朴葉餅製造の聞き取り調査を行いました。
この記事では、地元飛騨の伝統的な朴葉餅製造について、その製造過程から文化的意義まで詳しく探ります。
今回、お話を伺った餅屋は地産地消を心がけており、いまでももち米は飛騨産にこだわった「たかやまもち」を使っています。
人気の商品に「あねかえし」というものがありますが、これほどかというほど濃い緑色のまんじゅうです。
毎年2万個前後の朴葉餅を使っている餅屋さんの朴葉はどのように作られているのか調べてきました。
今回の調査でも餅屋さんのみなさんの採取過程、製造過程をお見せしていただくだけでなくいろいろな話を聞かせていただくことができました。はじめにここで、お礼を申し上げさせていただきます。
ありがとうございました。
餅屋との出会い
初めにお餅屋を訪れたのは6月の後半でした。
店に入ってお店の方を呼ぶと出てきたのはお母さん。
社長さんはあぶらえ栽培などで忙しく店を空けることが多いため、詳細なことはわからないという話でした。
また、朴葉餅の販売は7月になってからということで、その時期になったらまた連絡しますということで終わった。
代わりにお店の歴史について聞かせていただくことができました。
もともと60年前(1968年)に創業し、50年ほど前から今のような形で工業化して売り出し始めたそうです。
もともとは今の通りより中でやっていたのですが、30年ほど前にアクセスの良い今の場所に移動されました。
尾崎餅店さんの概要
- 営業時間 8:30~18:30
- 日曜定休(他不定休あり)
- 飛騨国府駅から徒歩12分
- 尾﨑餅店 - Google マップ
- 0577-73-2329

阪大の学長さんの話
私が京都大学の学生ということを知ると、西尾章治郎さんの話をしてくださいました。
この方は今の阪大の学長さんで、もともと国府町のこの部落の出身だそう。
斐太高校卒業後に京大工学博士という経歴でした。
2023年1月号 わたしの勉学時代 大阪大学 総長 西尾 章治郎先生に聞く|個別指導のDr関塾
この記事のインタビューで思い出の味について飛騨のことを答えており、地元への愛着が感じられます。
――思い出の味は?
郷里の飛騨高山の名物「中華そば」と「みだらしだんご」。そばは昔ながらの醤油スープと細ちぢれ麺が特長です。だんごは炭火で焼いた香ばしい醤油味がして、関西の「みたらしだんご」とは別物です。
後日、朴葉採取に同行させてもらう
それから、幾日か経ったので少し「忘れられてしまったかなー、そろそろ飛騨での日数も少なくなってきたのでこちらから連絡してみようかな」
と思っていた矢先、電話で朴葉採集に行きますのでどうですか?と連絡をいただきました。
後から話を聞いてみると今までの朴葉採集の日は悪天候だったため声をかけるのに忍びなかったそうです。
ご配慮ありがとうございます。
車に乗せてもらって目的の畑へ向かいます。
林道をさらに奥へ
朴葉畑(森)への道中にいろいろとお話を聞かせてもらった。
今回の朴葉の採集枚数は600枚。
翌日の朴葉餅製造で全部使うためだといいます。
国府町から20分ほどの場所にある畑へ向かいます。
道中は未舗装の林道を走るのでがたがた道。
畑は10年前に作ることになりました。もともとはホオノキとホオノキの木々を飛び移ってとっていたのですが、それを見かねた父が危ないからといって朴葉の畑を作り始めました。買った土地を択伐してホオノキを残した跡地に、林業組合から買ったホオノキの苗を植えたのが10年前。今年が最初の収穫です。
畑を見るとたしかに大きなホオノキと小さなホオノキが生えています。
朴葉採取

今回葉を採集したホオノキ。この木に登って枝を落とした。
朴葉採取の流れはこんな感じ。

まずホオノキの枝を地面に落とす。
地面に落ちた枝から葉がついた先端をとって集める。
そこから使える大きさ、きれいさの葉だけを集めてかご(袋)に入れていく。
今年は芯止め(: ホオノキの芯となる中心の太い木をある程度の高さのところで切ることでそれ以上、上に伸びにくくして葉を低い位置からでも取りやすい形の樹形にすること)
をする予定でした。
そのため、芯止めする部分より上の方はいつもより大胆に切り落としていました。
他にも芯止めをする目的としては風に煽られたときに折れてしまうのを防ぐという目的もあります。
よく見ると風で倒れてしまったホオノキもありました。
風で倒れたホオノキ。新しい葉がもこもこと出ている。
ただ一番の択伐の目的は「持続可能性」です。
息子の代になったときでも息子をホオノキに登らてせて危険な作業を指せることなく、朴葉が採れるようになるはずです。
息子はまだ見に来たことが数回あるだけですが、私が年齢を感じてもうできないな、って感じたら息子にやってもらうつもりです。
私が飛騨に来てから半年が経って、始めて地元の人から「持続可能性」という言葉を聞きました。
正直みんな次の世代がやっていけるか、のような狭い視野での「持続可能性」にばかり気を取られて、広い視野の、文化や環境、社会規模、地球規模の視点での「持続可能性」の話をする方は少ないなというのが私の印象でした。
その中でとくに広い視点を持って「持続可能性」にこだわっている方だというのが私の今回受けた強い印象です。
ホオノキの管理
ホオノキの管理でやっているのは、下刈りと液肥。
下刈りは近くに住んでいる知り合いの方にお願いしているそう。
液肥は、葉をとると木は必然的に弱ってしまうため、栄養をあげているそう。
大事なのは液肥にすること。
もともとホオノキは根が強く、肥料をあげると葉焼けしてしまうほどに吸ってしまう性質があるのですが、液肥を使うことで拡散が早くすぐに肥料が切れるため、葉焼けを防ぐことができます。
10年経った朴葉畑ですが、印象としては全然成長していない、です。
理由としては1つは盗伐があるけど、日当たりとか何かしら別の影響もあるのかも。
もう一つ別のところにある朴葉の畑と比べると全くホオノキの若木の様子が違います。

もう一箇所の畑の朴葉は、今回の場所と比べて明らかに大きい
盗伐
最近、『盗伐』という本を読んで日本での盗伐の事例が意外にも身近にあるものだと思っていたら、まさかの自分のもっと身近にありました。
今回の畑の見学でも、切られたホオノキの若木がざっと見る限りでも数本ありました。
勝手に切られたホオノキの後
昔は盗伐なんてなかったからね。
自分さえよければいいっていう身勝手な人が増えてこういうことが起こっているんだね。
「お天道様が見てる」とか「ばちが当たる」なんていう言葉も聞かなくなってしまったし。
昔は「おかげさま」っていう気持ちがあって、共存して生きていたはずなのにね。
今は時代が変わって他人と会話がなくても1人で生きていくことが用意になりましたよね。何かが足りないなら大型スーパーに行って買えばいい。
冬の雪が辛くても除雪車が来て車を出すことができる。
そんな暮らしの変化がひとびとの心のありようすら変えてしまったのかもしれませんね。
こういうわけで、今回の朴葉の畑の場所を明らかにすることは少しためらいがありました。
私の意見ですが、森に生えている小さなホオノキをとっていくのはある程度は許されると思っています。
飛騨地域ではホオノキは自然に生えてくるものであり、数も限られていません。
森の中であればそこまで手入れが行き届いているわけでもないからです。
ただ、今回の場所は明らかにホオノキがたくさん生えている管理された畑です。
こうした場所で私用目的で「朴葉がほしいから」ホオノキを切っていくのは犯罪ではないのでしょうか。
良心の呵責は無いのでしょうか。
登山道が近くにあるわけでもない、地元の人でなければ行かないような場所で起こったことであるからこそ、違う悲しさもあります。
朴葉餅
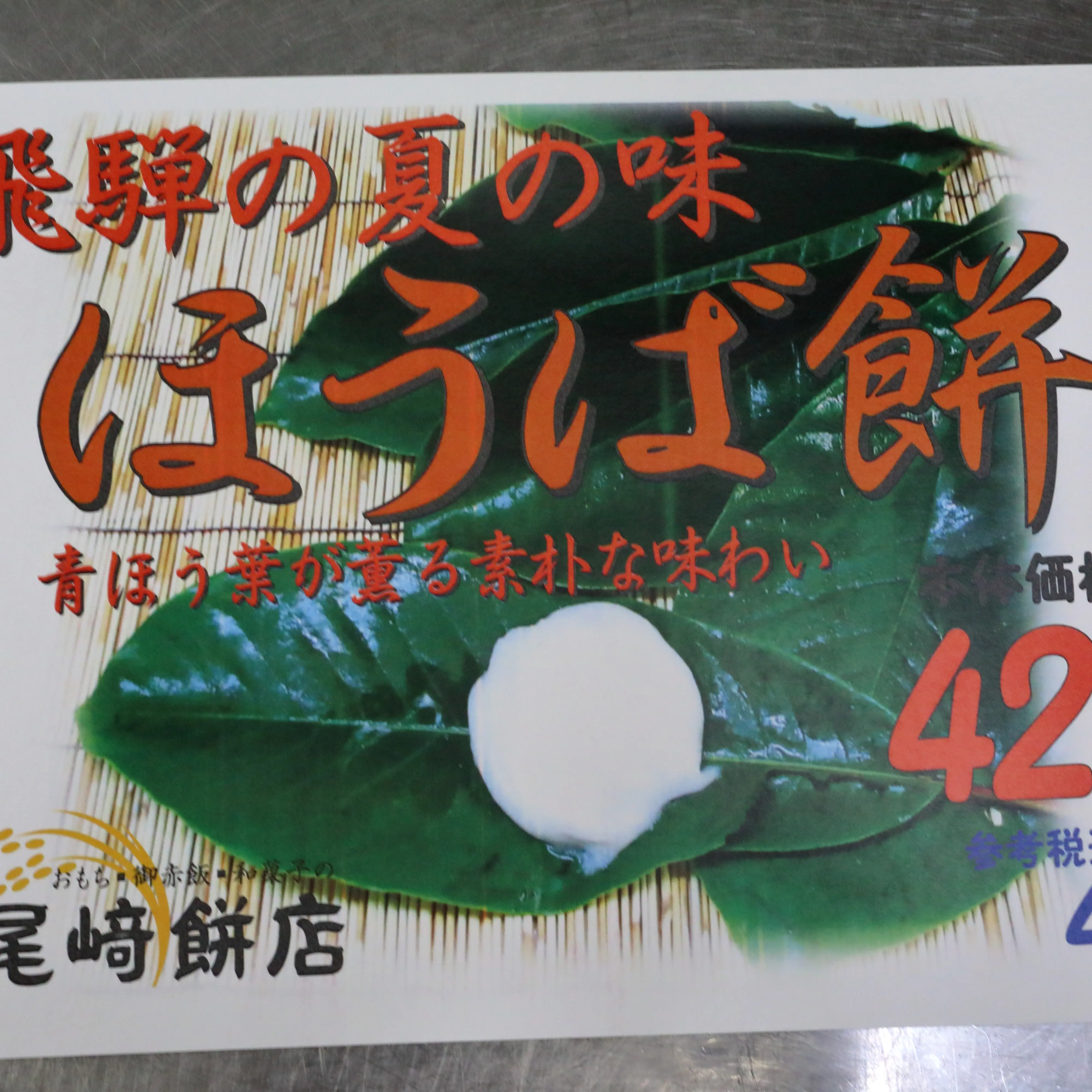
朴葉餅のお店で使うポップ、飛騨の夏の味
朴葉餅は葉に抗菌作用があって日持ちがするんですよ。
梅雨やお盆のような暑い時期でも長期間保存することができる昔の人の知恵を感じますよね。
実際は、朴葉の抗菌作用だけじゃなくて、葉っぱに密着させることによる空気に触れない効果も大きいらしい。
ここでは前日にとってきた朴葉を冷蔵保存しておいて、使う日に電解質の水で洗います。
そしてついた餅を重量で測ってちぎってまるめてのっけてくるむ。

餅を葉で包む
熱いままのせると色が変色してしまい見栄えが悪いのでお持ちは乗せる前も、挟んでからも扇風機で冷まします。
挟んだ後の朴葉餅はいったんここで冷ます
その次は、余分な部分の朴葉をハサミで切ります。
専用の朴葉台紙があるので、ざっとそれに合わせて切ります。
朴葉の葉の余った部分を台紙を使って切る
次に包装。専用のパッケージに5個ずつ入れて脱酸素剤を入れて空気を抜いて密封。
賞味期限(2週間)と価格(463円)のシールを貼り付けて完成です。
商品のパッケージ
みんなで一緒にやるので作業が早い。
お盆の最盛期になると高校生などを雇ってすべての作業を同時並行でやっていきます。
朴葉に穴がアイていたらその部分につけるパッチ朴葉
朴葉餅を作る理由
朴葉餅を作り続ける理由としては2つあって、1つは食文化って一瞬で消えるんです。
今はまだ朴葉餅をこうして作って飼ってくれて食べてくれる人がいるけれども、もし一瞬でもこれが途絶えてしまったら朴葉餅の文化を復活させることは難しいと思います。
そしてもう一つがコメを使うということが大事です。
もともと飛騨地域では昔からコメ栽培が盛んです。今はトマトやほうれん草なども栽培できるようになっているけれども、コメというのが歴史的には最近この地域でとれた農産物です。山が近くにあって水がきれいな場所なのでおいしいお米が採れます。
地産地消っていう考えはありますが、将来的に食料や肥料などを海外に依存していると他国から輸入できない状況に陥ったときに困るのは私達です。
そして、他国から輸入するというのは船や飛行機を使いますからそれだけ金銭的にも環境的にもコストがかかる。
こうした考えがあって、コメを使うということにもこだわりがあり、朴葉に関しても中国産に頼らず地域のものを使っていくのが大切だという考えがあります。
同じようにバウムクーヘンも餅屋の隣で作っていますが、そちらにも高山さんのうるち米を使っています。
小麦ではなくてうるち米をつかったバウムクーヘンというのはとてもめずらしいですよね。
先程の「持続可能性」という考え方と合わせて、とても素敵な考え方ですよね。
昔からその地域になぜその食文化があるかっていうことを考えると、間違いなく「その地域に合ったものだから」というのが答えです。
社会が変化して便利になったように見えても、その弊害を見えないどこかに押しやっているだけなことがほとんどです。
一見不便に見える昔のものがいかに社会に合っているかということをあらためて認識するきっかけにもなりました。
どうして朴葉がこの場所で使われているのか、もっともっと考えてみる必要がありそうです。
若い朴葉。彼らが次の時代を背負う。
徐々に減っていく朴葉餅
最近は徐々に朴葉餅を作る数も減っているそう。
消費者が減っているんだもんね。都会の消費客が減っている。今は煙が出ない料理じゃないと東京では作れないので朴葉餅もできない。
大戸屋(和食チェーン)に行く人の中には焼き魚が家でできないから外に食べに来たというお客さんもいるほど。
昔から食べていた飛騨の夏の味の朴葉餅ですが、その味を知る世代が徐々に亡くなっていき、若い世代は余り食べません。
先ほど言ったように朴葉餅のような焼く料理をしなかったり、そもそもしらなかったりするんですよね。
餅屋が高い志を持って、朴葉餅の文化を守ろうと努力をしているのに、私達消費者は答えないといけません。
地元になんのゆかりもないようなお土産や、環境負荷の高い牛に大きく依存している今の状況はほんとうに正しいのか?と考えさせられます。
おすすめの食べ方は雑煮
最後に食べ方を聞きました。
パッケージ裏にも書いてありますが、葉をつけたまままずはフライパンなどで焼きます。
そうするとだんだんと葉っぱがパカンとひらいて剥がれてきますのでそうしたら裏返します。
裏も焼けたら、次は葉を完全に外してお餅だけで焼きます。
これに砂糖醤油などをかけるのもいいですが、朴葉の香りを感じることができるので、なにもつけなくても十分に美味しいです。
おすすめの食べ方はなんと「お雑煮」
いれる具材はみょうがとあげ(油揚げ)と焼いた朴葉餅だけ。
この食べ方は初めて聞きましたが、みょうががいい感じの風味となって夏でもさっぱり食べられそうです。
ぜひみなさんもやってみてください。
尾崎餅店さんの朴葉餅は高山市内では
- さとう
- 駿河屋
- あじか
- ACOOP丹生川
- バロー(一部)
で買うことができます。
もちろん、本店に直接電話することもできますが、早めにしたほうが助かると思います。
地域の食文化や「持続可能性」を守っていくためにも、知っている人はもちろん、今まで朴葉餅をしらなかった人も朴葉餅を試してみてはいかがでしょうか。
今までもたくさんの朴葉関連の方にお話を聞かせてもらいましたが、今回も発見と驚きと尊敬に出会うことができました。
ありがとうございました。

もう一つの朴葉の畑の様子。